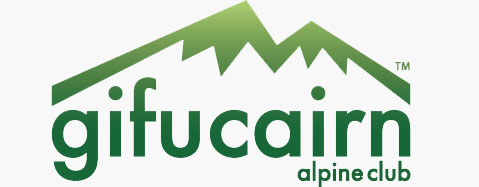雪山ハイク+山スキー:猿ケ馬場山
日 程:2025年3月29日
参加者:会員5名
Aリーダーの発案で、今年の冬たっぷり雪を蓄えた猿ヶ馬場山に行ってきました。3月25日頃、日本列島南部には大量の黄砂が降りましたが、山行前日に降った新雪がうっすらと雪面を雪化粧。綺麗な雪山を楽しむことができました。
本山行は、メンバー5人の足回りがユニークで、スキー1名、スノーシュー1名、スーパーカンジキ1名、ワカン2名とバラバラ。出発前からどうなることやらと心配になる山行でした。念の為トランシーバーを準備しましたが、見えなくなるほど離れることはなく(遅い僕を待ってくれたやさしいみなさんに感謝!)、出番はありませんでした。
猿ヶ馬場山で心配なのは駐車場です。登山口は合掌造りで有名な白川郷萩町なのですが、駐車場が開くのが午前8時。深いラッセルなどあろうものならとても頂上まで行けません。ところが、抜群の情報収集能力のあるKKさんが耳寄りな駐車場情報を仕入れてきてくれて、6時頃出発することができました。

まだ誰もいない萩町を通り抜け、まずは尾根沿いにルートをとります。スキーで直登は無理なのでジグザグを切って上がります。山廻りキックターン、固い雪面へのけり込みで、ワカン隊に遅れをとってしまいました。あとでログを比べたら余分に1km以上長く登っていました。

一方ワカン隊は急斜面を直登。スピードハイカーのKKさんを先頭にサクサク登ります。時々、遅れ気味のスキーメンバーを待ちながら登ります。

気温も低くガスの中の登りは、汗をかくこともなく快適です。しばらく登ると傾斜も落ち、この時期にしては珍しい樹氷が美しいブナ林となりました。

傾斜が落ちればスキーもラクラク。遅れることはなくなりました。

4時間ほどの登高で標高1,622mの帰雲山(かえりくもやま)に到着。この山の西面には2.5万分の1の地形図でもはっきりとわかる崩壊地があります。1586年の天正地震の際に大崩壊が発生し、麓にあった帰雲城が埋没したと言われています。お城には大判小判がザックザク。今も一攫千金を夢見て掘り返している人がいるとかいないとか・・・

帰雲山を過ぎると晴れてきました。青空に映える樹氷林の息をのむような美しさ!

ガスの下には今まで登ってきた山々が見え隠れして幻想的な景色です。

帰雲山から先はなだらかな稜線散歩。青空のもと快適な登高が続きます。

頂上台地からは雄大な白山が間近に望まれます

頂上には標識は見当たらなかった(雪の下?)のですが、360度見回してもそこより高いところはなく、自分の立っているところが頂上であることがわかりました。お決まりの記念撮影です

木陰で風を避け、KKさんが作ってくれた雪のベンチに座ってお昼ご飯です。

下山は登りの逆でスキーが先行します。数日前に黄砂が降りましたが、前日うっすらと積もった新雪のおかげでスキーもよく滑ります。初めて「黄砂用ワックス」を塗ってきたのですが、不要でした。

今日は気温が低く雪も締まって雪崩やブロック崩壊の心配はありません。下山には谷コースを選択しました。微妙なアップダウンがなく、スキーには嬉しい選択です。帰雲山の手前のコル付近から右手の尾根に入ります。美しい山々を望みながらの下降です。

尾根にはやや急な部分や樹林の濃い部分もありますが、木をポールに見立ててスイスイ滑ります。

尾根の末端は雪が切れていたので、少し手前で谷の中に入りました。念の為、側壁からの雪崩やブロック崩壊、雪の薄そうなところがないかに注意しながら降ります。スキーはハーフパイプのようにスーイスイとくだれました。

側壁からは古い雪崩が何箇所も出ていてデブリを乗り越えながらの下降が続きます。条件の悪い時は使えないルートですね。

萩町に降り立ちました。インバウンドの外国人観光客でごった返す中、場違いな5人が歩くとみな避けます(笑)。

下山後お蕎麦をいただき、暗くなる前に岐阜へ帰ることができました。
written by Kojima
おしまい🎶